
「古物商許可を取りたいけど、どんな準備が必要?」「警察署での申請が不安…」
そんな方のために、この記事では古物商許可をスムーズに取得するための実践的なコツをまとめました。
前回の記事「古物商の取得の流れを徹底解説|費用とスケジュール感までわかる完全ガイド」を読んだうえで、よりスムーズに申請を進めたい方におすすめの内容です。
目次
- 申請前に確認すべき3つのポイント
- 書類準備を効率化するコツ
- 警察署での申請をスムーズに進める方法
- よくあるミスと回避策
- 行政書士に依頼するメリット
- まとめ
申請前に確認すべき3つのポイント
古物商許可は誰でも簡単に取れるわけではありません。
スムーズに進めるためには、事前確認が重要です。
① 営業所(店舗・オフィス)の要件を満たしているか
- 自宅兼事務所の場合、「事業利用可」の契約が必要。
- 玄関やリビングと明確に区別されたスペースが理想です。
② 欠格事由に該当しないか
次の条件に該当する場合、古物商許可は取得できません。
- 過去に犯罪歴がある(一定期間内)
- 暴力団関係者
- 破産して復権していない
③ 営業形態を明確にしておく
「ネット販売のみ」「店舗販売」「出張買取」など、営業形態によって申請内容が変わります。
最初に明確にしておくと、書類の記入ミスが防げます。
書類準備を効率化するコツ
古物商申請の書類提出に際しては、事前準備ができていない場合、何度も役所に足を運ぶことになりがちです。
以下の手順で進めると効率的です。
① 書類リストをチェックしてから動く
- 管轄警察署のWebサイトまたは窓口で最新版の申請書類リストを入手。
- 個人/法人で必要書類が異なるので要確認。
② 役所の窓口を一日で回る
「住民票」「身分証明書」「登記簿謄本」などは、まとめて取得可能です。
平日午前中にまとめて回るのがコツ。
③ 書類の有効期限に注意
書類の有効期限は発行日から3ヶ月以内。
早すぎる準備は逆にやり直しになることもあります。
警察署での申請をスムーズに進める方法
警察署での対応をスムーズにするには、次の3つのポイントを押さえましょう。
① 事前に電話で確認する(マスト!)
提出先の警察署によっては、予約制・受付時間制限がある場合があります。
直接訪問する前に必ず電話で確認を。事前に電話をしないと、場合によっては1時間以上の対応待ちとなったり、最悪の場合窓口受付時間を過ぎてしまい別日に再訪ということにもなり兼ねません。時間は大切に・・・。(僕は事前に電話を忘れ、1時間以上待ちました・・・orz)
② 書類はクリアファイル等で整理&チェック
複数の書類を整理しておき、まとめて提出すると、担当者からの印象も良くなります。
さすがに書類不備で怒られることはないと思いますが、再訪を避けるためには、事前準備が重要です。なお、担当によっては、古物営業法の〇条について理解してる?等聞かれるようです。私は聞かれませんでした。
③ 服装・態度にも注意
ビジネスカジュアル程度の服装を心がけ、礼儀正しく対応することで信頼感が高まります。
許可を出すのは「警察」なので、印象は意外と重要です。
よくあるミスと回避策
古物商の申請でつまずく人が多いポイントを事前に知っておきましょう。
| よくあるミス | 回避策 |
|---|---|
| 書類の押印忘れ | 提出前に必ず印鑑チェックリストを使用 |
| 営業所の所在地ミス | 物件住所を住民票・契約書と照合 |
| 記載内容の不一致 | 個人番号・氏名の表記を統一 |
| 書類の有効期限切れ | 発行日を記録してカレンダー管理 |
行政書士に依頼するメリット
「自分で手続きするのが不安」「忙しくて時間が取れない」
そんな場合は、行政書士に依頼するのも一つの方法です。僕個人としてはおすすめしていません。
メリット
- 書類作成・申請をすべて代行してもらえる
- 警察署への確認や補正対応も任せられる
- 書類不備による再提出リスクを減らせる
費用相場
行政書士への依頼費用は3〜5万円前後が一般的。
自分で行うより費用はかかりますが、細かい手続きをまるっと誰かにお願いしたい場合は有効です。
まとめ
古物商許可をスムーズに取るためのポイントは、次の3つです。
- 事前準備を徹底する(営業所・欠格事由・形態確認)
- 書類を効率的にまとめて取得する
- 警察署へ行く前に確認と整理を行う
これらを押さえれば、初めての申請でもスムーズに許可を取得できます。
具体的な流れやスケジュールを知りたい方へ:
→ 古物商の取得の流れを徹底解説|費用とスケジュール感までわかる完全ガイド
それではまた!

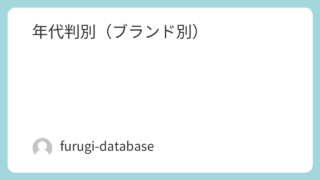
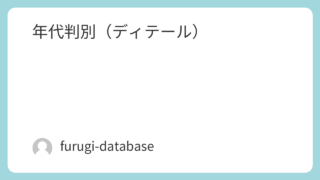
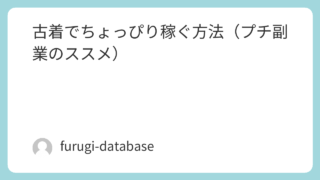
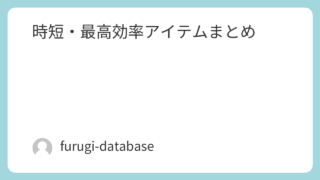
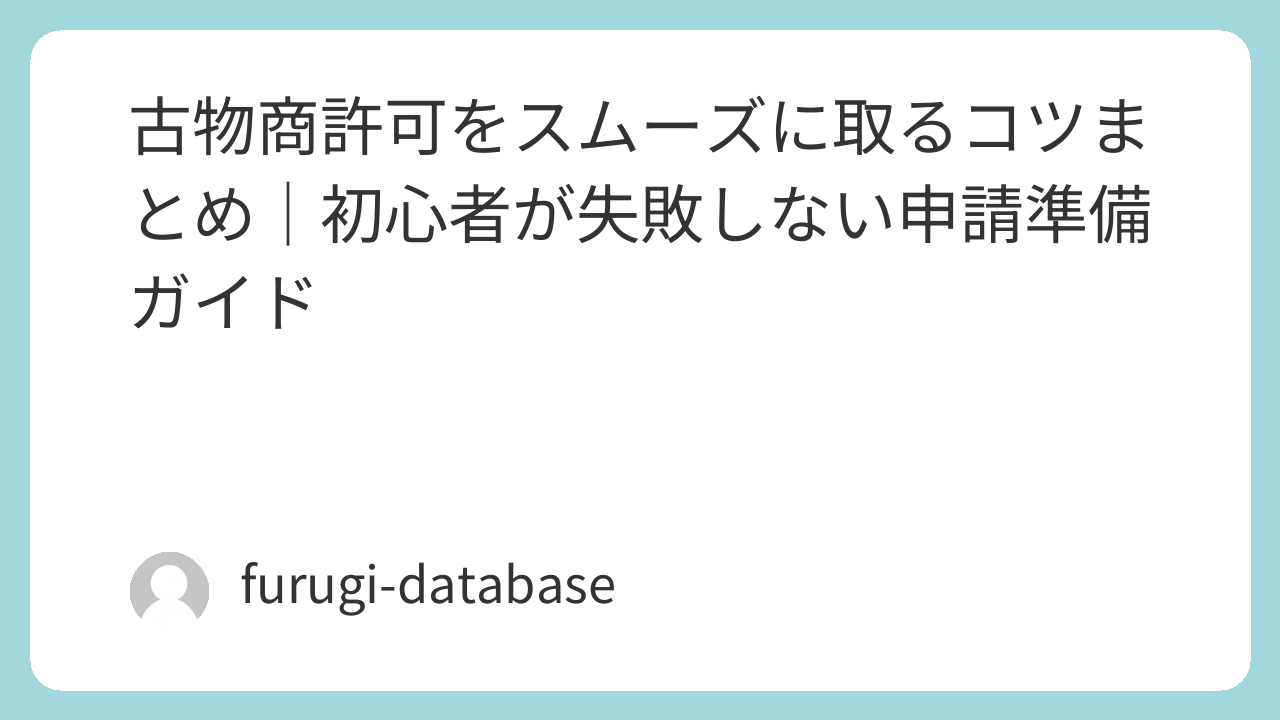
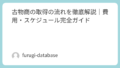
コメント